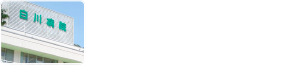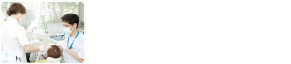当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
機能強化加算について
- ■ 他の医療機関の受診状況および、お薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。
- ■ 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
- ■ 必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
- ■ 介護・保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。
- ■ 夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供します。
※かかりつけ医機能を有する医療機関は、都道府県の医療機能情報提供システムにて検索できます。
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定支援、身体拘束最小化について
当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が協同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。
意思決定支援について
当院では、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めております。
身体的拘束最小化の取り組みについて
当院では、多職種による身体拘束最小化チームを設置し、緊急やむえない場合を除き、身体的拘束を行わない取り組みを行っております。
明細書発行体制について
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬算定項目の判る明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書は、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。その点をご理解いただき、ご家族等が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行をご希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
当院は、東海北陸厚生局に以下の届出を行っております。
施設基準について
入院時食事療養(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出
当院は、入院時食事療法(Ⅰ)の届出を行い、以下の基準に沿って食事を提供しております。
- イ)食事は医療の一環として提供しており、管理栄養士によって管理された食事を適時・適温で提供しております。
- ロ)病状に応じ必要な栄養管理、喫食調査等を行いながら食事の質の向上・患者さんへのサービスの改善を行っております。
- ハ)当院より提供する食事については、医師及び管理栄養士による検食を行っております。
- ニ)給与栄養目標量について必要に応じ見直しを行っております。
- ホ)病状等により特別な食事が必要な方については、医師の指示により適切な特別食を提供しております。
- ヘ)食事の提供時間:
- ト)食事療養標準負担 510円(一食当たり)
入院料について
2階病棟
地域一般入院基本料3を算定しています。
当病棟には、1日に10人以上の看護職員が勤務しています。
朝8時30分~夕方17時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち患者数は、7名以内です。
夕方17時30分~朝8時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち患者数は21名です。
3階病棟
療養病棟入院基本料2を算定しています。
当病棟には、1日に8人以上の看護職員が勤務しています。
朝8時30分~夕方17時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち患者数は、7名以内です。
夕方17時30分~朝8時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち患者数は51名です。
保険外負担に関する事項について
-
(1) 診断書・証明書及び保険外負担に係る費用
-
(2) 入院期間が180日を超える場合の費用の徴収
入退院支援加算1について
個人情報相談窓口について
当院では患者さんと医療従事者との対話を促進するために医療福祉相談室に「個人情報相談窓口」を設置しております。個人情報の取扱いに関すること、転院や施設紹介に関することなど、お気軽にご相談ください。
協力対象施設入所者入院加算について
栄養サポートチームによる診療について
当院では、栄養障害の状態にある患者さんや栄養管理をしなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者さんに対し、患者さんの生活の質の向上、原疾患の治療促進及び感染症等の合併症予防等を目的として、栄養管理に係る専門的知識を有した多職種からなるチーム(医師、歯科医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、歯科衛生士、言語聴覚士など)が適切な栄養療法を行うための活動を行っております。
医療安全管理・院内感染防止対策に関する取り組みについて
当院では、安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全管理委員会(セーフティー・クオリティー委員会)と連携し、より実効性のある医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。当院では、感染防止対策委員会を設置し、院内感染状況の把握、職員の感染経路別予防策等をおこない、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っております。また、院内だけにとどまらず感染防止対策につき感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携しています。
後発医薬品、一般名処方加算について
当院では、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして、入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しています。ご不明な点がございましたら。主治医または薬剤師にお尋ねください。
医療DXによる医療情報の有効活用について
当院では、医療DXを推進及び活用した質の高い医療の提供を目指しております。 医療DX整備体制については、以下の通り対応しております。
- ① オンライン請求を行っております。
- ② オンライン資格確認等システムを行う体制を有し、取得した医療情報を診察を行う診察室などにおいて閲覧または活用できる体制を有しております。
医療情報を正確に取得及び活用することにより、質の高い医療の提供に努めます。そのため、院内にポスターを掲示し、マイナ保険証の利用を推進しております。 - ③ 電子処方箋を発行する体制については、現在導入に向けて検討中でございます。
- ④ 電子カルテ情報共有サービスを導入及び活用する体制については、現在検討中でございます。
在宅医療DX情報活用加算について
当院では、在宅DX情報を活用した質の高い医療の提供を目指しております。 在宅DX情報活用加算については、以下の通り対応しております。
- ① マイナ保険証利用を推進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- ② 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施しています。
- ③ 電子処方せんの発行や電子カルテ共有サービスなど医療DXにかかる取り組みについては、現在検討中でございます。